
第7作 「男はつらいよ 奮闘編」
さて、第7作目です。
公開が、1971年の4月ですから、第6作目からわずか3ヶ月後。
寅さん映画というと、その公開時期に合わせて、真夏の暑い盛りと、暮れから正月にかけての風情が描かれていることが多いという印象でしたが、本作は、随所に桜や花見などの春の風情が切り取られていて、寅さん映画としては珍しい季節感の作品かもしれません。
この時期の松竹は、まさに寅さんにおんぶに抱っこで、封切れば客の入りが見込める寅さんシリーズは、まだまだヘビーローテーション。
定番のお盆と正月のローテーションが始まるのは、まだもう少し先のことのようです。
さて、7作目ともなると、寅さん映画も、かなりフォーマットが定着してきます。
それと同時に、マンネリの波もヒタヒタと押し寄せる頃です。
しかし、それを回避するために、あまり大胆なキャラクターいじりや、ストーリー展開を取り入れるようなことをすると、テレビ時代からの寅さんファンは納得しないでしょう。
この辺りが寅さん映画の難しいところです。
決まったフレームから決してはみ出さない範囲で、いかに新鮮さや面白さを作り出してゆくか。
観客を決して飽きさせずに、結局は、それを48作にわたってやり続けたわけですから、やはりこのシリーズは偉大です。
その意味では、制約された条件の中で、本作はかなり冒険的なアプローチをした作品になりました。
今回のマドンナとなった榊原るみは、ここまでではシリーズ最年少。
予告編では、「大型新人登場」と謳っていましたが、彼女は本作公開時20歳です。
渥美清とは、20歳以上も歳の離れた、娘のようなマドンナが登場したわけです。
しかも、彼女が演じた太田花子は、軽度の知的障害者です。
そんな彼女を、東京の下町という、ある意味では野蛮な世界へ放り込み、しかも、到底立派な大人とは呼べない寅のような粗忽者と絡ませようというわけですから、出演者の台詞回しは、相当周到に練られたことと思います。
「男はつらいよ」シリーズは、全作山田洋次監督のオリジナル脚本ありきだったわけですが、そのあたりを踏まえてか、いよいよ本作において、共同脚本として、朝間義隆がキャストに加わります。
以降彼は、シリーズの全作の脚本を、山田洋次監督と共同で、執筆していくことになります。
この黄金コンビによるシリーズ初の共同脚本となったのが本作です。
ナイーブで、ある意味で非常にデリケートな内容となった本作は、この若きマドンナへの周囲の視線が、決して差別的で不快なものにならないように、レギュラー以外の役者にもかなり気を配ったキャスティングがされているのもポイントでしょう。
寅が花子と初めて出会うラーメン屋の店主には、落語会の重鎮だった柳家小さん。
花子を保護する沼津駅前交番の警官に、クレイジーキャッツの犬塚弘。
花子の出身地青森の小学校の担任だった福士先生に田中邦衛。
新人榊原るみの純真無垢な演技は、このベテラン俳優陣によって支えられていたかもしれません。
もちろん渥美清の演技も絶品。
一歩間違えれば、差別表現とも捉えられるようなギリギリのセリフを、絶妙な言い回しで喜劇演技に昇華させる演技力は流石の一言。
そして、本作のもうひとつの見どころは、ここまでの6作のマドンナたちを、台詞の上できちんと登場させていること。
そして、その代表として、第二作で、寅の母親お菊を演じたミヤコ蝶々と、第一作目のマドンナ冬子を演じた光本幸子を再登場させています。
シリーズ映画を、最初から順番に見てくると、こういうサービスは、なんだかとても嬉しくなってしまうもの。寅さん映画は、大河ドラマなんですね。
思わずニンマリです。
これが、山田氏、朝間氏、どちらのアイデアかは知る由もありませんが、この第7作は、寅さんシリーズの「お約束」は踏まえた上で、果敢にマンネリ打破に「挑戦」しています。
さて、本作の冒頭は、雪深い新潟県の越後広瀬駅。
集団就職を見送る家族たちの一団の中に寅さんがいます。
プロの俳優は渥美清だけで、その他は全てノンクレジットであろうエキストラの人たち。
この素人たちに、泣いたり笑ったりの感情表現演技をさせて、まるで違和感を持たせない撮り方のできるところが山田洋次監督のすごいところ。
さながら、ドキュメンタリーのような映像です。

クレジットが終わると、帝釈天参道のとらやの前に高級車が横付けされます。
車から降りてきたのは、キラキラの洋装に身を包んだ高齢の女性。
第二作で登場した、寅の実母お菊です。
彼女は、若かりし頃、この葛飾柴又で芸者をしていて、遊び人だった寅の父親の子供を産んでいます。
それが、我らの車寅次郎というわけです。
つまり、妹のさくらは、寅とは腹違い。
そんなわけで、菊とは一面織もなかったさくらは、寅の嫁に間違われてしまいます。
それもそのはず、寅は「嫁をもらうことになるかもしれない」という葉書を、一年前に菊に出していたのです。
はて、一年前というと❓
とらやの面々は、歴代マドンナたちを指折り数えて、一体誰のことだろうと思案。
考えてみれば、寅さんはここまでわずか一年半の間に、すでに6回も失恋を経験しており、そのうちの何人かは、寅が勝手に結婚まで考えていてもおかしくはないという展開でした。
もしかしたら、寅の嫁に会えるかもしれないと、とらやを訪ねたお菊でしたが、いまだに息子は全国を旅している風来坊のままだと知り、自分が宿泊しているホテルだけを告げて、柴又を後にします。
そんなとらやに寅がフラリと帰ってきます。
とらやの面々も、心の中ではいつも寅を快く迎えてやろうとは思っていても、いざ寅が帰って来てみると、必ずチグハグな展開になり、結局ヘソを曲げる寅。
また「夏になったら泣きながら、必ず帰ってくるあの燕さえも・・」と、言いかけてところへちょうど、里帰り中の御前様の一人娘冬子(初代マドンナ光本幸子)が息子を抱いて登場。
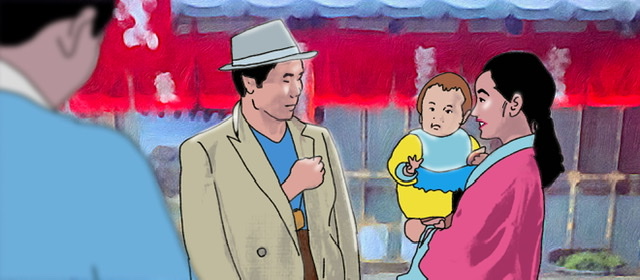
一瞬で満面の笑顔になって機嫌を直してしまう寅に、とらや一同も呆れ顔です。
結局とらやに腰を落ち着ける寅ですが、さっそくマイペースで、周囲の日常を混乱させてしまいます。
裏の朝日印刷の工場に顔を出しては、仕事の邪魔をしたり、訪ねて来た菊のことで寅の心配をするさくらの前で、特大の屁をこいたりとやり放題。
結局、寅はさくらと一緒に、菊の泊まっている帝国ホテルに向かうことになります。
ちなみに、第二作のラストではなかなか「いい関係」に復活しているように見えた寅とお菊の親子でしたが、本作においてはまだシコリが残っているという設定になっていますね。
お菊と会っても心ここに在らずの寅を、一生懸命フォローするさくら。
しかし、話し込む二人の横で、寅は悪ガキののように悪戯三昧。
久しぶりに会った親子ではありましたが、結局は口論になってしまいます。
「おまえ、ちょっと脳が足らんのと違うか。」
「脳が足りねえとはなんだ。脳が足りねえ息子を産んだのはどこのババアだ。」

なんでもない親子喧嘩の言い合いですが、この後の展開を考えると、このセリフは巧みな伏線になっていてドキリとさせられます。
口喧嘩はエスカレート。こういう展開になると、関西弁のミヤコ蝶々の台詞回しは迫力満点。
結局「てめえがワッと驚いて腰抜かすようなベッピンの嫁つれて来てやるから、腰抜かすなよ」という捨て台詞を残して、寅はホテルの部屋を飛び出してしまいます。
残されたさくらは、寅の気持ちを慮ってお菊に向かって猛抗議。
しかし、お菊は必死なさくらのその様子を見て、そっと涙を浮かべます。
「さくらちゃん、おおきに、おおきに。」
「嫁を探しにいってくる」と言い残して、旅に出た寅は、静岡県の富士市で啖呵売をしています。

さてその夜、沼津駅近くのラーメン屋で夕食をとる寅の横で、若い女の子が一人でラーメンを食べています。
本作のマドンナ太田花子です。演じるのは榊原るみ。
彼女はちょうど本作の公開された年にテレビ放映された「帰って来たウルトラマン」に出演していたの覚えています。
何かしらのシンパシーを感じたのか、花子は寅に向かって笑いかけます。
店主(柳家小さん)がお釣りを取りに行っている間に、寅に駅までの道を訪ねる花子。
風呂敷包みを大事そうに抱えて出てゆく花子を心配そうに見送る寅ですが、戻ってきた店主が、花子のただならぬ様子に感づき、寅にボソリ。

「そのうち悪い男に捕まって、バーだキャバレーだ。挙げ句の果てはストリップにでも、売り飛ばされちゃうんじゃねえかな。」
ラーメン屋の入り口近くには、ストリップ劇場のポスターもさりげなく貼ってある辺りは、美術担当の芸もなかなか細かい。
心のどこかに花子のことが引っかかったまま、寅が駅前を歩いていると、駅前交番に保護されて泣いている花子が目に飛び込んできます。
居ても立ってもいられなくなって、警官と花子の間に割って入る寅。
警官を演じているのは犬塚弘です。

名前と住所を聞き出した寅は、花子がラーメン屋の店主の言う通り、近くのバーで働いていて、そこから逃げ出し、故郷の青森へ帰ろうとしていることを知ります。
花子の所持金では、青森までは帰れないと知ると、警官と自分の所持金を足して切符を買ってやる寅。
それでも、一人で青森まで帰れるかどうか心配な寅は、ついていってやりたくても、有金を叩いてしまっているため自分の切符は買えません。
「かつしか。しばまた。とらや」という走り書きのメモを渡し、迷子になったら、近くの警官にこれを見せて、そこへ連れていってもらえと花子を見送る寅。
その花子の目に浮かぶ涙を見て、寅の胸は締め付けられます。
「とらちゃーん。とらちゃん居るべか。」
数日後、寅の走り書きしたメモを握りしめた花子が、突然とらやに現れます。
思わず顔を見合わせるとらやの面々。
花子に軽度の知的障害があることを理解した一同は、とりあえず花子の言う青森の住所の役場に速達を送ることにします。
そんなところへ、もしや花子が寄ってはいないかと心配になった寅が帰ってきます。
寅と再会した花子は、満面の笑顔。
自分の娘のような年齢の純真無垢な花子に、父性を掻き立てられる寅。
すっかり花子の保護者気取りの寅に、さくらたちも心配を隠せません。
翌日から、花子の働き先を見つけてやろうと奮闘する寅。
しかし、花子を心配するあまりの、寅のお節介は案の定暴走し、とらや周辺をかき回すだけ掻き回すだけ。
結局、花子はとらやで働くことになります。
江戸川の土手に座って語り合う二人。
故郷津軽の岩木山や、小学校の担任教師福士先生のことを嬉しそうに寅に語る花子。
その大好きな福士先生には奥さんがいることを告げると、花子はついポロリと寅に言ってしまいます。
マドンナのセリフとしては、寅さんシリーズの中でも、屈指の衝撃的一言。
「あたス、とらちゃんのよめっこになるかなあ。」

これは、寅にとっては、完全にカウンターでした。
花子の障害のことなどケロリと忘れて、すっかりその気になってしまう寅。
花子の一言に、感極まって、寅は自分の思いの丈を語り出します。
「俺が一生面倒見るから、ずっとここにいろ。もうどこへも行くな。」
しかしそれが、寅の「愛の告白」などとは、夢にも思わない花子。
一旦スイッチが入ってしまえば、もはや自制心がカケラも働かないのが、寅さんの悲しいところ。
「嫁を連れてくる」と啖呵を切った母親のお菊には、そのことを電話で伝えてしまいます。
そして、さくらと博のアパートまで出かけて、なんだかんだとアパート暮らしのリサーチをしながらも、ヤニ下がってしまう始末。
寅が結婚を考えている相手が、まさかの花子だということを知ると、さくらと博の顔にも不安がよぎります。
ひとたび恋愛のスイッチが入れば、啖呵売にも気合が入る寅。
寅が商売に出ている間に、花子の小学校の担任だった福士先生が、とらやを訪ねてきます。
さくらたちが、花子の故郷の役場に送った速達を受け取っていたのが福士先生(田中邦衛)でした。
ヨモギ摘みから戻った花子は、誰よりも(おそらく寅よりも)会いたかった故郷の恩師の顔を見てビックリ。
「花子。迎えに来たぞ。」
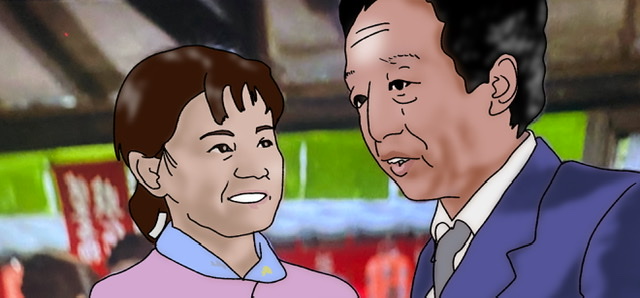
彼女のその大きな瞳からはみるみると大粒の涙です。
その後、2人が話し合っている東北弁の会話は、僕には外国語みたいで聞き取り不能。
とらやの面々は、寅のことを考えると複雑な表情。
しかし、学校にすぐ戻らなければいけない福士先生は、そのまま花子を連れて、寅に会うこともなく青森へ帰って行きます。
そこへ、商売を終えた寅が帰ってきます。
もうとらやに花子がいないことを、なかなか言い出せないおいちゃんたち。
結局そのことを寅に説明したのはさくらでした。
納得できない寅は、一同に振り返ってこう言います。
「お前たち、嫌がる花子を無理やり返したな。」
そうでもいわなければ、自分の気持ちを抑えられない寅。
博がそれをキッパリと否定しますが、治まらない寅は、さくらたちに食ってかかります。
花子は自分と一緒にいるよりも、故郷に帰った方が幸せに暮らせるとでも思っているのか。
そう迫る寅に向かって、さくらは涙を堪えながら、毅然として言い放ちます。
「そうよ。その通りよ。お兄ちゃん。」
かくして、寅のシリーズ7回目の失恋が、ここに悲しくも成立。
旅に出ようとする寅を止めようとするさくら。
その手を払おうとして挙げた寅の手が、さくらの頬を打ちます。
僕の記憶にある限り、寅が妹さくらに手をあげた唯一のシーンだったかもしれません。
数日後、とらやに速達が届きます。
もちろん旅先の寅からです。
消印は、青森県津軽郡。寅は、やはり花子に会いにいっていました。
「花子は元気にしていたし、俺はもう用のない人間だ。生きていても仕方がない。」
しかし、その内容はまるで遺書そのもの。
さくらは、おいちゃんたちに背中を押されて、そのハガキを握りしめ一人青森へ向かいます。
さあ、これからが本作のクライマックスになっていくわけですが、なんとここからラストシーンまで、寅さんは一切登場しないという展開になるのが、この脚本の考え抜いたところ。
ここからは、さくらを主人公とするロードムービーになります。
前年に、彼女を主役にして、山田監督が撮ったロードムービー「家族」のタッチです。
奥羽本線弘前駅から、ローカル五能線に乗り換えて、驫木へ向かうさくら。
日本海を望む駅から、村の人たちに道を尋ね尋ね、なんとか福士先生の勤める田野沢小学校を探し当てます。
花子は、そこで元気に働いていました。思わず目を細めるさくら。

寅はやはりここを訪ねていました。
福士先生は、職員室で寅が訪ねてきた時の様子をさくらに伝えます。
そこへ、花子が入ってきますが、さくらを見ても、モジモジして言葉が出ません。
普段はよく喋るけれど、よその人が来ると、急に口数が少なくなるという花子。
それは寅が訪ねて来た時も同じでした。
自分の顔を見れば、必ず花子は満面の笑顔で「とらちゃん」と喜んでくれることを確信していた寅にとってこれはショックだったはず。
柴又では、花子の心の拠り所であった「とらちゃん」も、故郷に帰ってきてしまえば、ただのよその人になっていたのです。
寅の今回の失恋は、このマドンナゆえの残酷なものでした。
花子への未練立ち難く、ここまでやってきた寅は、ここで「もう自分は用無し」とはっきり思い知らされることになります。
もちろんそのシーンが、本作の脚本に用意されていれば、芸達者な渥美清のこと、その切なさを完璧に表現する演技を見せて、観客を泣かせてくれたことと思います。
しかし、本作ではその悲しいシーンは描かれませんでした。
あくまで、さくらの視点から観客にそれを想像させたわけです。
本作のラストの展開には、倍賞千恵子に対する、山田監督の絶大な信頼が感じられますね。
帰りのバスの中、寅の安否に一抹の不安を拭いきれないさくら。
バスから見える千畳敷の海岸では、上がった水死体の周りに、人々が集まっています。
ま・・まさか。
そして、バスが近くの温泉の停留所に止まると、さくらの耳に聞こえてきたのが寅の声でした。
温泉客と一緒に、バスに乗り込んできたのは、紛れもなく「生きている」車寅次郎。
バスの中で顔を見合わせる二人。
寅の送ってきた遺書のような葉書を突きつけて、寅を責めるさくら。
そのさくらの勢いに、申し訳なさそうにする寅。
「俺、死んだと思ったか❓」
「冗談じゃないわよ。」
怒りながらも、花べそ半笑いのさくらを見て、寅も満面の笑顔。
「死ぬわきゃねえよな。」

この最後のセリフとこの会心の笑顔の為に、寅の出番をここまで引っ張ったというところでしょう。
そして、寅とさくらを乗せたバスは、弘前へ・・・
このラストは、テレビドラマ版では、最終回で寅を殺してしまったことでファンからのクレームを浴びた山田監督が、この国民的ヒーローはもう二度と殺すことはありませんよと、ファンに改めて宣言をしているのだとも思えましたね。
ここまでの寅さんシリーズとしては、なかなか異色のラストでした。
個人的な映画の好みを申し上げますと、子供や動物の可愛さやあどけなさで引っ張る映画は好きではありません。「御涙頂戴」の難病ものも好きになれません。
それで微笑ませたり、泣かせたりするのは、映画作りとして反則だろうと思うわけです。
同じように、障害者を主人公にした映画も、それで観客を感動させようというのは、やはり映画作りとしては安易ではないかと思ってしまうところがあります。
今回あえて山田監督は、それを承知でマドンナに障害者を設定。
その意味で本作は、非常にデリケートな作品になりました。
しかし、考えてみれば、寅さんだからこそ、今回の太田花子がマドンナ役として成立したとも言えます。
高倉健や石原裕次郎では、花子の相手役は務まりませんね。
本作において、寅はマドンナに対して、初めて事実上のプロポースをしています。
その意味では、「美人」でありさえすれば、寅のマドンナに、タブーはないのかもしれません。
フェデリコ・フェリーニ監督の「道」を再見してみたくなりました。
太田花子とジェルソミーナがなんだかダブります。
さて次作は、第8作目「男はつらいよ 寅次郎恋歌」です。