
○ さよならベイビー
さて、前作「私をスキーに連れてって」が大ヒットしたおかげで、本作の企画は、かなり強気に行けたようです。当然予算もそれなり。
ヒロインは、前作に引き続き原田知世。相手役には織田裕二がキャスティングされました。
「私スキ」が、冬の雪山を舞台に、ユーミンの既存の曲をドンピシャリではめて大ヒットさせたとあれば、今回は夏の海でサザンというわけです。
主題歌になった「さよならベイビー」は、本作のために桑田佳祐が書き下ろし曲だったんですね。
というわけで、前作では、「挿入曲 ユーミン」というクレジットでしたが、本作では「音楽 サザンオールスターズ」になっていました。
映画の中に、織田裕二扮する吉岡文男が、原田知世扮する田中真理子と行き違うシーンがあるのですが、桑田佳祐との打ち合わせの時、馬場氏はこのシーンを熱弁したそうです。
後日、出来上がってきた本作のためのオリジナル曲「さよならベイビー」の歌詞を見た馬馬氏は、この曲がそのシーンを想定して書かれた曲であることに気づきます。
実は、このシーンには、桑田佳祐のソロでのヒット曲「いつか何処かで(I FEEL THE ECHO)」を使うことが初めから決まっていたので馬場氏は頭を抱えたとのこと。
しかし、編集担当の冨田功が「この曲、頭でいけますよ」の一言で、オープニングのタイトルバックに採用ということになったとYouTubeの番組で言っていました。
冨田氏が、歌詞の「大人になれない」の部分に合わせて「監督 馬場康夫」のタイトルを出したなんていう茶目っ気ある裏ネタを聞いて、DVDで確認しましたがまさにその通り。
そんな裏話を聞かされると、一度見た映画でも、また違った楽しみ方ができて、嬉しくなってしまいます。

○ 海洋冒険アドベンチャー
真理子は、友人の石井恭世(伊藤かずえ)と一緒に参加した相模湾でのスキューバー・ダイビングで、インストラクターたちとはぐれてしまいます。
海底をさまよう二人は、海底に沈んでいるダグラスDC-3の残骸を偶然発見。
実はここには、50億円のお宝が・・
この情報を知り、そのお宝を見つけて一攫千金を狙うのが、クルーザー「ツバメ号」のオーナー大塚(谷啓)と、アマゾン号のオーナー山口(伊武雅刀)。
そして、ここに謎の中国人グループが加わり、三つ巴のお宝争奪合戦が始まります。
なので、今回は前作のようなリゾート系ラブロマンスというよりは、007のようなアクション映画の方に、かなり軸足が寄っています。
若き日の馬場氏が、007シリーズに如何に傾倒していたかというのは、仲間たちと作っていた自主制作映画のタイトルを見ても明らか。
その作品のほとんどが、007シリーズのパロディです。
登場するアイテムも、前作成功の勢いに乗って、冒険活劇向けに、かなりのスケールアップ。
ヘリコプター、クルーザー、水上オートバイ、潜水艇、ホーバークラフトなどなどが、次々と登場します。
クルーザーの中では、ボタンひとつで、ベッドとバーが出現。
もう、ここまでくると、完全にスパイ・アクション映画のノリですね。
完全にジェームズ・ボンドの世界です。
その分、主人公二人のラブロマンス・パートが薄まってしまった感は否めません。
馬場監督も、この作品は「海洋冒険アドベンチャー」と、自身のYouTubeチャンネルで言い切っていました。
本作では、ウォーターフロントでの水上チェイスシーンで、大活躍したのが水上スキー。
映画で使われたのは、KAWASAKI JS550 SX とX-2。
日本で発売されたのが、ちょうど映画公開の前年ですから、まさにこの時点では最先端の乗り物。
個人的には、この映画の公開された翌年に、初めてハワイに行った時に、ハナウマ・ベイで乗ったことがあります。
まともに乗れなくて、コケ続けている映像が、ビデオに残っています。
アメリカでは、1970年代からあったようですが、ハワイでは、水上オートバイではなく、ジェット・スキーと言ってました。
⚪︎ プロダクトプレイスメント
ちなみに、本作のように、製品やサービスを映画中に登場させることで、ブランド認知度を高め、商品の宣伝をするマーケティング手法をプロダクトプレイスメントと言います。
この手法は、1950年代からありました。
しかし、これを徹底的に活用するあたりの映画づくりは、さすがは広告業界出身の馬場監督ならではの手腕。
映画の中で登場する自動車や飲料、ファストフード店などは、すべて契約したスポンサー企業の商品になっていますね。
ツバサ号の船底には、堂々と「バドワイザー」のロゴをペイントするシーンがありました。
プロダクトプレイスメントは映画制作の費用を補うこともあり、当然劇場での集客や、スポンサー側では、商品の販売促進につなげることができるわけです。
今でこそ、商品のタイアップは、映画やドラマでは当たり前の手法ですが、これを「あたりまえ」にしたのは、ホイチョイの功績だったかもしれません。
時代は、バブルでパンパンに膨らんでいたわけです。
三菱地所が、ロックフェラー・センターを買収したのもちょうどこの年。
今は、国際的には見る影もない日本企業ですが、この頃は絶好調で、ジャパン・マネーの威力を世界に響かせていたわけです。
そんな時代の勢いが、この作品にはプンプンしていますね。
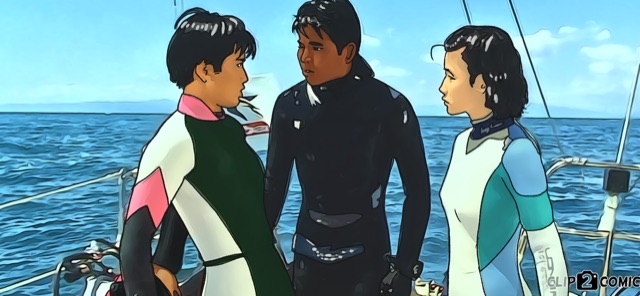
⚪︎ スキューバー・ダイビング
スキューバー・ダイビングは、人生でたった一度だけ経験しています。
場所は、バリ島です。
ここで、日本人が経営していたダイビング・スクールの一日体験ツアーに参加しました。
実際に潜る前に、インストラクターと「耳抜き」の練習をするのですが、相方は難なくクリアしているのに、なかなか要領がわからなくて少々焦りました。
不安のまま、人生で初めて酸素ボンベを背負って海の中へ。
初心者は、常にインストラクターと繋がっていなければいけないのですが、僕のアシストをしてくれたのが、日本で女優をしているという綺麗なお姉さんだったのでドキドキしたのを覚えています。
ハワイでは、シュノーケリングまではしていますが、本格的な海中は生まれて初めて。
楽しみにしていたマンタやサメなどの大物には会えませんでしたが、カエルアンコウやミノカサゴが、目の前を悠々と泳いでいく姿はバッチリ。
ニモやドリーといった可愛い魚たちも見ることが出来ました。
この体験が強烈だったので、日本に帰ってきてから、一緒に行った当時の相棒と、スキューバーダイビング・スクールに体験入学をしましたが、月謝が高くて、一回行っただけで断念しました。
ちなみに、本作の海中シーンは、全て沖縄で撮影しています。
沖縄も行きましたが、人生で一番綺麗な海を体感したのは、実は沖縄の離島慶良間諸島のビーチでした。
海底の珊瑚が、海上のボートから肉眼で確認できましたね。
映画では、相模湾の海底という設定になっていましたが、これはすぐに違うところで撮っているとわかりました。

⚪︎ 谷啓
ツバメ号のオーナー大塚を演じたのは谷啓。
どこまで本気で、どこまで冗談かわからないような、掴みどころのない自由人といった役どころです。
クルーザーを所有しているわけですから、かなりのお金持ちのはずですが、実際何をしているのかは映画では説明されません。
老境に差しかかろうかという年齢なのに、若くて美人な奥様(田中美佐江)がいます。
馬場監督は、俳優のキャスティングには、1ミリも関わっていないと言っていましたが、ホイチョイ三部作のキャスティングで、唯一プロデューサーに、自分の希望をお願いしたのが大塚役の谷啓だったとのこと。
YouTube番組でも、馬場氏は、ミュージシャンであり、コメディアンでもある谷啓に、最大級のリスペクトを送っていました。
谷啓といえば、もちろんハナ肇とクレイジーキャッツのメンバーです。
しかし、彼の元々のルーツは、日本屈指のジャズ・トロンボーン奏者。
クレイジーに参加後は、コントの脚本なども書いていた多彩な方です。
実は、ホイチョイの名前の由来は、人気絶頂期の彼らのコミック・ソングに頻繁に登場する「ホイ」だの「チョイ」だのという意味不明の合いの手を合わせて、もじったものだとのこと。
僕も覚えている谷啓の最大のギャグといえば、なんといっても「ガチョーン」。
さすがに本作には登場しませんでしたが、追い詰められた彼が、タメにタメてから放つ「ガチョーン」の切れ味は、一発ギャグとしては最高レベル。メチャクチャ好きでしたね。
⚪︎ 冒険者たち
本作を鑑賞すると、1967年のフランス映画「冒険者たち」のテイストがプンプンします。
本作を作るにあたっては、馬場監督もこの映画を相当に意識していたのは確実。
この「冒険者たち」に出演しているのが、ハンサムな色男アラン・ドロンと、みずみずしい魅力のヒロイン、ジョアンナ・シムカスと、中年の自動車技師リノ・バンチュラ。
谷啓演じる大塚は、さしずめリノ・バンチュラでしょうか。
三人が、海底に沈められたお宝を探して、冒険を繰り広げるのも、本作と同じ展開です。
「冒険者たち」では、中年のリノ・バンチュラは、当然のように若い二人を応援して、自分は一歩ひきます。
しかしヒロインは、自分と同世代の若いアラン・ドロンではなく、年老いたリノ・バンチュラと一緒に暮らしたいと告げるんですね。
ジョアンナ・シムカスの顔が、ちょっと田中美佐江と重なってしまいました。
⚪︎ お宝探しはアドベンチャーの原点
1979年に、三浦友和、紺野美沙子、藤竜也の出演で作られた「黄金のパートナー」という映画がありましたが、この映画も、「冒険者たち」にオマージュが捧げられ海洋お宝探し映画でした。
現在一線で活躍中の映画監督たちの中にも、「冒険者たち」のファンは、案外多いように思います。
お宝探しは、スティーヴンソンの「宝島」の昔より、冒険アドベンチャーとしては、定番中の定番。
子供から大人まで楽しめるエンターテイメントとして、古今東西の映画に取り上げられ続けています。
ちなみに、本作に登場する2台のクルーザー「ツバメ号」「アマゾン号」は、アーサー・ランサムが、1930年代から執筆を開始した、子ども向け冒険小説シリーズ「Swallows and Amazons」に因んだもの。
イギリス北部の湖沼地帯を舞台に、冒険や船旅を繰り広げる様子を描いています
全12話の中には、海賊が埋めた宝を探すエピソードもあり、読書好きの少年だった馬場氏も、おそらくは胸躍らせて当時の岩波少年文庫を読み漁っていたのでしょう。

⚪︎ 俳優たち
さて、この大塚の宿敵となるクルーザー「アマゾン号」の所有者・山口を演じたのが伊武雅刀。
この人は、僕らの世代では、なんといっても「スネークマン・ショー」。
放送コードギリギリの危ないギャグは、なんともシュールで、ぶっ飛んでいました。
しかし、アニメ・ファンなら、伊武雅刀といえば、やはり「宇宙戦艦ヤマト」のデスラー総統ということになるかもしれません。
吉岡と大塚の海仲間の役で出演している竹内力は、この頃はまだ甘い端正なマスクなお兄ちゃんでしたが、のちにVシネマの極道役に活路を見出し、思い切りドスを効かせた顔芸で、哀川翔や小沢仁志などとと並んで、「Vシネマの帝王」と呼ばれるようになっています。
その悪役ヅラの大先輩でもある安岡力也も、本作では、とぼけた役でワンシーンのみ出演していますね。
主演の織田裕二と原田知世について、語っていないじゃないかと言われそうですが、原田知世については、「私スキ」のところでたっぷり語らせてもらいました。
織田裕二については、この次に書く予定の「波の数だけ抱きしめて」のところで、しっかり語りたいと思いますので、ここでは割愛いたします。
⚪︎ 若大将シリーズが原点
馬場氏は、クレイジーキャッツの一連の映画同様、60年代の東宝のドル箱だった「若大将」シリーズの大ファンだったとも語っていますが、監督の弁によれば、このシリーズは、馬場氏にとっては、ファッションや若者文化の教科書だったというわけです。
ストーリーそのものよりも、使っているグッズ、着ている服、乗っている車、楽しんでいるスポーツの細かいディテールに注目して映画を作るというホイチョイイズムは、若大将シリーズが、案外その原点にあったと言っていいのかもしれません。
若大将が、青大将の横槍を蹴散らして、すみれちゃんの愛を勝ち取るという鉄板ストーリーよりも、青大将の渋いアイビーファッションの着こなしや、乗っているアメ車の方に興味の目が行けば、映画は全く違うものに見えるのかも知れませんね。

⚪︎ ホイチョイ式映画作り
自分たちの趣味嗜好にとことん寄せた映画作りこそが、ホイチョイ・プロダクションの真骨頂です。
そして、自分たちの「イケてる」「かっこいい」「好き」に対する徹底的なこだわりこそが、ホイチョイのクリエイティブの原点と言ってもいいでしょう。
そのこだわりを極上の「売れ線」エンターテイメントに昇華させてしまうセンスの良さこそホイチョイ映画の面目躍如です。
とにかく、映画のアイデアが、過去に馬場氏が「かっけえ」と思った映画のシーンを上手に加工再生したもののオンパレードになるので、映画ファンとしては目が離せません。
馬場氏のYouTubeチャンネルを聞いていると、彼の目から見た映画批評も、なかなか面白いんですね。
元祖「七人の侍」よりも、リメイクの「荒野の七人」の方が面白い。
溝口健二の良さがいまだに理解できない。
「東京物語」は、この歳になってもやはり苦手。
「トップガン マーヴェリック」は、それほどでも・・
ジム・ジャームッシュはつらい・・
反対に、馬場氏が推薦する「面白い」映画も、一般的な世間の評価とは、微妙にずれていて、これがまた興味深いわけです。
一度見ている映画でも、馬場氏のフィルターを通して、再度その面白さを解説されると、こちらは思わずまた見たくなってしまうんですね。
そこにも、幾つになっても自分の「好き嫌い」には、徹底的に正直でいようとする馬場氏のこだわりが伝わってきます。
⚪︎ 正しい映画の鑑賞方
僕などは、かなりの見栄っ張りですので、何かと世間一般の評価には左右されてしまいがち。
実際自分にとっては「面白くなかった」映画も、その歴史的評価を学習したウケウリで、心にもなく「面白かった」などと言ってしまいがちなところがあります。
これは大いに反省ですね。
考えてみれば、映画という娯楽の評価には、そもそも正解などありません。
どこをどの楽しもうと、何をどう感じようと、それは見た人の自由に委ねられるべきもの。
どんなに傑作であろうと、面白くなければ、それはその人にとってはそういうもの。
反対に、どんなに周囲で酷評されていようと、その映画に見るべきところが発見できれば、面白い映画になる可能性だってあります。
こちらも、そろそろいい歳ですから、その辺り、馬場氏を見習って、自分の感性には正直に行こうと思います。
これからも、老人の道楽で、映画の感想はまめにブログにしていくことになりますが、多少ピントがはずれていても、それはそれ。
面白さがわからなければ、それは単にこちらの感性が劣化したか、あるいは成長が止まっているかのどちらか。そこは、そう開き直った上で映画を楽しむことにいたします。
まあ、あまりにトンチンカンだっ場合は「ハラホラヒレハレ」ということで。
(このギャグを、わかる人だけわかっていただければ・・)
